バスケットボールの世界でよく聞く「ランアンドガン(Run and Gun / R&G)」。
一方で誰もが知っている「速攻(ファストブレイク)」。
この2つはどちらも“速い攻撃”をイメージさせるため、しばしば同じ意味と勘違いされがちです。
しかし、実際にはこの2つは戦術の階層自体が異なる概念です。
厳密な公式定義があるわけではありませんが、当サイトでは次のように整理して解説します。
ランアンドガンと速攻の違いは?(結論)
当サイトでは、両者の関係を次のように整理します。
- 速攻(ファストブレイク):特定の状況で使う「個別の戦術手段」
- ランアンドガン:試合全体のテンポを上げ続ける「チーム全体の哲学・システム」
つまり、ランアンドガンは“常に速攻の状況を作り続けようとするシステム”であり、
速攻はその中のひとつのプレー(手段)にすぎません。
速攻とは?どんなプレーを指す?
速攻の定義と目的
速攻は、リバウンドやターンオーバー直後に、相手の守備が整う前に一気に攻撃する戦術です。
2対1や3対2などの数的優位を作り、レイアップなどの高確率ショットを狙うことが基本です。
速攻はすべてのチームが使う「機会的な戦術」
速攻は、どんなプレースタイルのチームでも使う、いわば“全チーム共通のオプション”です。
相手のミスが起きたとき、ラインブレイクできたときなど、状況が整えば自然と生まれます。
つまり、速攻はあくまで「状況が生んだ戦術」であって、
「常に速く攻めよう」というチーム哲学ではありません。
ランアンドガンとは?速攻と何が違う?
ランアンドガンは“システム全体の名前”
ランアンドガンは、単に速く攻めるだけのプレー名ではなく、チーム全体のスタイルを指します。
特徴は以下の通りです。
- とにかく攻撃テンポを上げる
- ショットクロックを使い切らず、早い段階でシュート
- 速攻が止まっても、そのまま早期攻撃を仕掛ける
- 守備でもフルコートプレスを使い、強制的にテンポを上げる
- ポゼッション数(攻撃回数)を最大化し、得点を増やす
つまりランアンドガンは、ゲーム全体のテンポを常に加速させ続ける“攻守一体の哲学”なのです。
“速攻の発生をこちらから作りに行く”のがランアンドガン
速攻は通常、相手のミスが起きたら自然とスタートします。
しかしランアンドガンは、フルコートプレスなどを使い、こちらから相手のミスを誘発し続けることで
速攻の機会を“量産”しようとします。
ここが、単発で生まれる速攻との決定的な違いです。
ランアンドガンと速攻の違い(整理表)
| 項目 | 速攻(ファストブレイク) | ランアンドガン(R&G) |
|---|---|---|
| 位置づけ | 特定状況で使う戦術 | チーム全体の哲学・システム |
| 頻度 | 機会があれば使う | 常に使い続ける前提 |
| ゲームテンポ | 一時的に上がる | 試合全体を高速化し続ける |
| ディフェンス | ミスが起きてから発動 | フルコートプレスで能動的にミスを作る |
| ハーフコート | 必要ならセットプレー | セットより早期攻撃を優先 |
歴史的にはどんなチームがランアンドガン?
ショータイム・レイカーズ(1980年代)
マジック・ジョンソンを中心とした高速トランジションで人気を博したチーム。
ただしレイカーズはカリームという守備の要がおり、攻守のバランスが取れた“正統派ランアンドガン”です。
ロヨラ・メリーマウント大学(LMU/ポール・ウェストヘッド)
「7秒以内にシュート」を徹底した伝説的R&Gチーム。
フルコートプレスで大量のターンオーバーを生み、NCAA史上でも最高速度級のペースを実現しました。
マイク・ダントーニのフェニックス・サンズ(2000年代)
“7 Seconds or Less” オフェンスを確立し、速攻+3P+スペーシングという現代バスケの原型を作りました。
ドン・ネルソン(ネリー・ボール)
ポジションを崩し、フロアスペーシングとスモールラインナップでテンポを最大化した革新的スタイル。
まとめ:ランアンドガンと速攻の違いは「哲学」と「範囲」
最後に、当サイトでの整理をもう一度まとめると——
- 速攻=特定の状況で発生する単発の攻撃手段
- ランアンドガン=速攻を常態化し、試合テンポを加速し続ける哲学・システム
似ているようで、実は“プレー”と“スタイル”という明確な差があります。
ランアンドガンは速攻を内包しつつも、攻守両面でペースを支配しようとする、より包括的な戦術思想なのです。
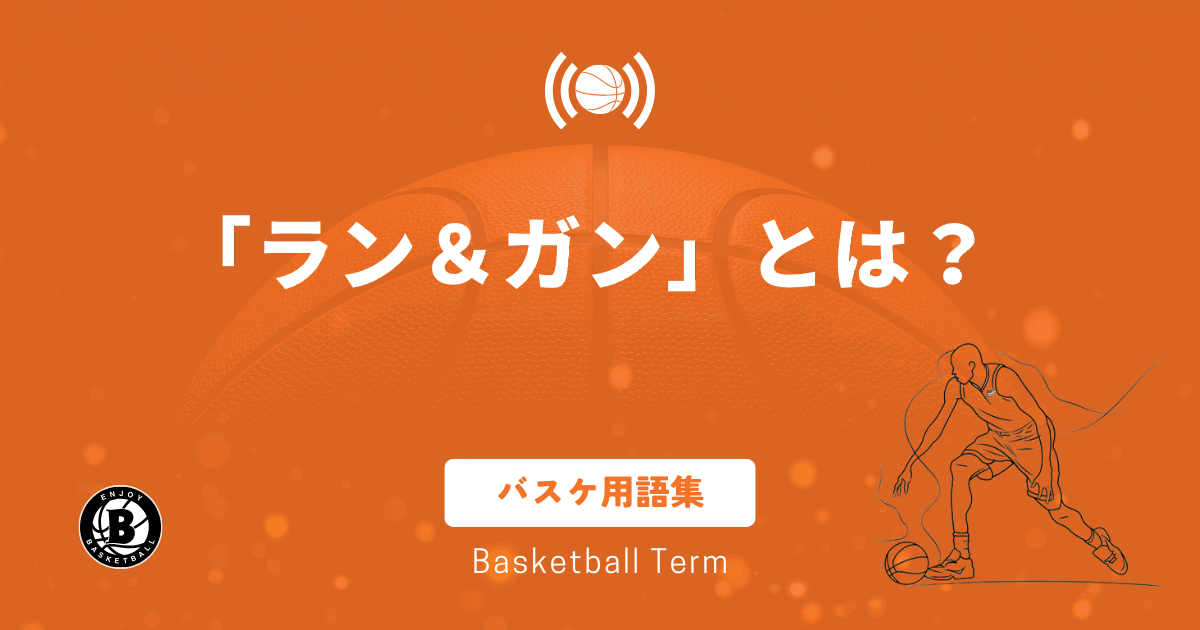
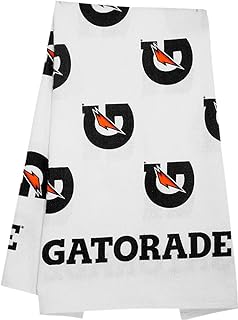

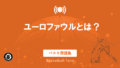
コメントはお気軽に ご意見やご感想、ご質問などはこちらへお寄せください。