バスケットボールの試合において、ツー・フォー・ワン(Two for One)戦術をうまく実行することで、試合終盤の得点機会を増やすことができます。
本記事では、ツー・フォー・ワンの意味やその効果に関する統計と研究を紹介します。
バスケ用語の「ツー・フォー・ワン(Two for One)」とは?
バスケットボールにおけるツー・フォー・ワン(Two for One)とは、試合の残り時間が少ない時に早めにシュートを打ち、もう一度自分のチームの攻撃機会が回ってくるのを狙うテクニックです。
だいたい残り35~40秒のときに、ボールを持っているチームがツー・フォー・ワン狙いのシュートを打つかどうか考えます。
ツー・フォー・ワンの語源
「ツー・フォー・ワン(Two for One)」という用語は、もともと「1つ買ったら2つついてくる」というお得な買い物のプロモーションから来ています。
この概念をバスケットボールに応用したものです。
ツー・フォー・ワンをうまく実行することで、攻撃の回数が1回多く回ってくるという事ですね。
ツー・フォー・ワンの実行手順
- 早めにショットを打つ:残り時間が約35~40秒のときに、できるだけ早く(通常は10秒以内に)ショットを打ちます。これにより、相手チームが攻撃した後、自分たちに再びボールを持つ時間が確保されます。
- ディフェンス:相手チームが次の攻撃を行う際にディフェンスをしっかり行います。
- 最後の攻撃:相手チームの攻撃が終了した後、通常はショットクロックが約24秒残っているので、自分たちの最後の攻撃の時間が確保されます。この時点で、時間をかけて確実に得点を狙います。
ツー・フォー・ワンの目的は、試合の最後の1分間や重要な局面で、相手チームよりも多くの得点機会を持つことです。この戦術をうまく活用することで、試合の流れを有利にすることができます。
ツー・フォー・ワンに関する統計・研究
NBAのデータ分析ブログ「Jay’s Life」の筆者であるJay Boice氏によると、ツー・フォー・ワン戦術について、効果的に実行できれば得点機会を増やすが、シュートの質が低下するリスクもあると結論付けています。
また、相手チームに得点機会を与えるリスクも考慮する必要があると述べています。状況に応じてこの戦術を使うかどうかを慎重に判断することが重要だとしています。
ツー・フォー・ワンでの得点増加の期待値はわずか0.8点だが…
Jay Boiceの分析によると、ツー・フォー・ワン戦術をうまく実行することで、得点が増加する期待値は平均で約0.8ポイントです。
(2008-2011年のNBAシーズンにおける約3,000試合のデータを使用。)
つまり、ツー・フォー・ワンを実行しても1点増えるかどうかというわずかな効果しかありません。
2008年から2011年という今よりも3ポイントシュートの数が少なかった時代を考慮しても、意外に少ない期待値です。
しかし1点の違いが天国と地獄を分けるのもバスケットボールというのも事実です。
だからこそツー・フォー・ワン戦術のような緻密な戦略が重要となります。
試合の終盤で冷静な判断と的確なプレーを実行することで、勝利への道を切り開くことができます。
バスケットボールの醍醐味は、こうした瞬間にこそ現れるのかもしれません。
ツー・フォー・ワンに関する議論・デメリット
Jay Boice氏も指摘しているように「ツー・フォー・ワン(Two for One)」戦術については、バスケットボール界で様々な議論があります。
以下は巷で議論されているツーフォーワンの主なデメリットです。
- シュートの質が低下する:ツー・フォー・ワンを狙うことで、早めにシュートを打たなければならず、結果として十分な準備やパス回しを経ない質の低いシュートを選択することが多くなります。これにより、実際の得点率が下がる可能性があります。
- 防御へのリスク:相手チームにボールを渡す時間が増えるため、相手チームも同様に得点のチャンスを持つことになります。特に、ディフェンスがうまく機能しなければ、相手に簡単に得点されるリスクが高まります。
- 時間管理の難しさ:ツー・フォー・ワンをうまく実行するためには、非常に精密な時間管理と状況判断が求められます。選手が焦って早めにシュートを打ちすぎたり、逆に遅れてしまったりすることで、効果が半減する場合があります。
- チームのリズムが乱れる:通常の攻撃リズムを変えてまでツー・フォー・ワンを狙うことが、チーム全体のリズムを崩す可能性があります。特に、試合の重要な局面では一貫したプレイが求められるため、リズムの乱れは大きなデメリットとなり得ます。
これらの理由から、一部のコーチやアナリストは、ツー・フォー・ワンが必ずしも最良の戦術ではないと考えています。
レブロン・ジェームズによる分析
高いバスケIQで知られるレイカーズのレブロン・ジェームズも自身のポッドキャスト番組「Mind the game」でもツー・フォー・ワンの得点チャンスの価値について深く掘り下げた会話を展開しているので紹介します。
要約すると、レブロンはツー・フォー・ワンの意味については熟知しているものの、効果的なのは時と場合によるというコメントを残しています。
以下、レブロンの発言まとめ。
クォーターの終わりにおけるツー・フォー・ワンのシュートが本当に嫌なんだ」
「ツー・フォー・ワンが重要なのは理解している。数の上では、自分たちが2回のポゼッションを得て、相手チームが1回のポゼッションになる。理論上は、それはフリーショットになるからだ」
「でも、多くの人が時々見落とすのは、その前の4~5回のポゼッションだ。私たちが連続得点中か?勢いに乗っているか?直近の2分半で良いシュートを決めているか?」
「もし直近の2分半から3分で良いシュートが打てておらず、ボールを何度も失っているなら、なぜショットクロックが33秒残っている段階で40フィートからシュートを打つべきなのか?それよりも良いシュートチャンスを狙うべきだろう。」
「なぜなら、第3クォーターの終わりに良いシュートを打つことができれば、それがたとえ1回のショットでも、第4クォーターに向けて勢いをつけることができるかもしれないからだ。」
このようにチームや試合状況に応じて、適切な戦術を選ぶことが重要です。
さいごに まとめ
ツー・フォー・ワン戦術は、試合の終盤で攻撃回数を増やすための有効な手段ですが、シュートの質やディフェンスへのリスク、時間管理の難しさなどのデメリットもあります。そのため、状況に応じてこの戦術を使うかどうかを慎重に判断することが重要です。適切な判断と実行によって、勝利への道を切り開くことができます。バスケットボールの醍醐味は、このような戦略的な駆け引きにあります。
最後までお読みいただきありがとうございます。
ツー・フォー・ワン戦術について、あなたはどのように感じましたか?
ご意見やご質問がありましたら、ぜひコメント欄にお寄せください。
皆さんのフィードバックをお待ちしています!

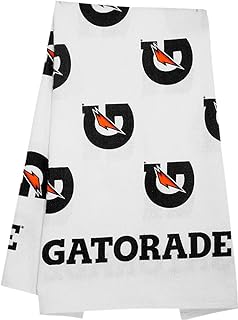

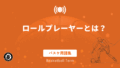
コメントはお気軽に ご意見やご感想、ご質問などはこちらへお寄せください。